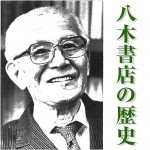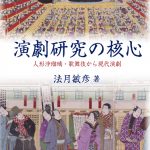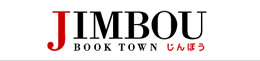-
紙魚の昔がたり
2018/01/1
樋口一葉の日記など 【紙魚の昔がたり18】
(八木) それで、そのうちに何か埋め合わせするからってことだったんですが、まだ何もない。……それでその時の目録は現在でも私の手元にあります(笑い)。もうひとつ別の失敗談があるんです。終戦後の、第一回の芥川賞をもらわれた由起しげ子さんの受賞作で、「本の話」という題の小説があります。そのモデルになってし […]
-
古書通信
2017/12/19
職人と芸術家 新刊『江戸・明治の視覚 銅・石版万華鏡』について【日本古書通信 編集長だより24】
先ごろ、森登さんのライフワークの集成ともいうべき『江戸・明治の視覚 銅版・石版万華鏡』を刊行した。正確に言えば、森さんは元中央公論美術出版のベテラン編集者だから、製作は全面的に森さん自身で担当し、装丁もシンプルなのが好きな私の好みに合わせてくれたのも有難かった。 森さんとの出会いは、当時神奈川県立 […]
-
紙魚の昔がたり
2017/12/4
五島慶太と張り合う 【紙魚の昔がたり17】
(反町) グループ共同仕入を実行して成功したのは、桑名の松平家、有名な白河楽翁さんの家の本。ずいぶんの大口で、小石川のお屋敷にあったもの。その全部を五十万円か六十万円かで買った。それは、そっくりまとめて、天理の中山正善さんに売りました。すでにそういう実績があった。で、急に皆さんに呼びかけて、金を出し […]
-
古書通信
2017/11/27
芭蕉師走の一句と朔太郎【日本古書通信 編集長だより23】
芭蕉、四十六歳元禄二年師走の句に 何にこの師走の町へ行く鴉 という句がある。今栄蔵著『芭蕉年譜大成』(平成6年、角川書店)によれば、元禄二年十二月大津・膳所滞在中の四句の一つ、同三年一月二日荷兮宛書簡中の二句の一つ、同三年一月十七日万菊丸宛の書簡中の六句中の一句として挙げられている。成書への初集 […]
-
紙魚の昔がたり
2017/11/6
五〇〇万円の大口 【紙魚の昔がたり16】
(八木) それと同時に、松坂屋時代の、子規よりももっと大きな思い出は、久原文庫のことです。現在の大東急文庫の基礎になっている大蒐集ですが、当時すでに久原家の都合で、所有権は親戚の藤田家に移っていて、現物は京都大学に寄託してありました。この頃、二十二年かと思いますが、藤田さんの方でお金が入り用で、売り […]
-
あの作家は●月生まれだった
2017/10/25
あの作家は●月生まれだった<11月編>
今月ご紹介する作家は、泉鏡花・武島羽衣・寺田寅彦の3名です。 泉鏡花(いずみ きょうか) 明治6年11月4日(一八七三)生 昭和14年9月7日(一九三九)没 小説家。本名鏡太郎。石川県金沢市下新町生。紅葉門下たらんと上京し、玄関番として小説修行に励む。明治大正昭和を通じて、文壇の流行と一定の距離を置 […]
-
古書通信
2017/10/24
沖縄・末吉麦門冬の俳句【日本古書通信 編集長だより22】
昨年本誌8月号に、沖縄の新城栄徳さんが「バジルホール来琉200周年 来琉記を平和のサチバイ(先駆)に」をご寄稿下さった折、新城さんのお仕事の中に、明治大正期の沖縄のジャーナリストで俳人でもあった末吉麦門冬(1885~1924)に関するものがあるのを知った。新城さんが編集発行する「琉文手帖」2号(1 […]
-
立正大学・古書資料館の世界
2017/10/24
仏教学者・河口慧海の旧蔵書【立正大学・古書資料館の世界 2回】(小此木敏明)
1.河口慧海の旧蔵書 第1回で土屋鳳洲について触れた際、河口慧海(えかい)の少年期の師、という紹介の仕方をした。河口慧海は近代の仏教学者で、最初にチベットに入国した日本人としても知名度が高い。そのため、鳳洲を慧海の師として紹介したのだが、慧海の名前が思い浮かんだのには別の理由がある。 実は、立正大学 […]
-
紙魚の昔がたり
2017/10/2
子規庵の子規草稿本を引出す 【紙魚の昔がたり15】
(反町) その話をモ少しして下さいな。子規庵の本をあなたが引出したことは、明治物の市場では、特筆すべき大きな事件ですから。どういう経路で……。 (八木) 御承知の通り、根岸の子規庵は戦災でやられて、焼けてしまいました。ですが庭に土蔵がございまして、中に入れてあった原稿類は、幸いに全部無事に助かったわ […]
-
古書通信
2017/09/29
川柳研究「すげ笠」について【日本古書通信 編集長だより21】
先日の古書即売会で、愛知県犬山で発行されていた川柳研究誌「すげ笠」の昭和23年2月(第三巻二号)から昭和32年5月号(第十二巻五号)まで9年間71冊を購入した。初めてみる川柳誌だが、終戦直後の占領期からもはや戦後ではないと言われた時代まで、川柳史を概観できるのではないかと思ったのである。71冊あって […]
-
あの作家は●月生まれだった
2017/09/28
あの作家は●月生まれだった<10月編>
今月ご紹介する作家は、織田作之助・上林暁・平林たい子の3名です。 織田作之助(おだ さくのすけ) 大正2年10月26日(一九一三)生 昭和22年1月10日(一九四七)没 小説家。大阪市南区生玉前町生。第三高等学校中退。大阪の市井を舞台とした「夫婦善哉」で世評を得る。戦後は太宰治、坂口安吾、石川淳らと […]
-
出版部
2017/09/14
観客の目線と感動を求めて(桜美林大学教授 法月敏彦)
1.「観客の目線と感動」 この度、長年の夢であった論文集『演劇研究の核心 ―人形浄瑠璃・歌舞伎から現代演劇―』を出版していただけることになりました。この本は、2017年3月に定年退職した玉川大学勤務40年間の研究成果をまとめたものです。 その要点は「観客の目線と感動」という言葉に集約できると思います […]
-
紙魚の昔がたり
2017/09/4
ウブな大口仕入の数々 【紙魚の昔がたり14】
(八木) で、仕入の方は、他の店があまり広告をやらない時代に、朝日新聞の東京版と地方版を使って、相当盛んに広告したもんですから、月に何回もトラックで運ぶような大口の仕入がありましてね。一つ二つをあげて見ますと、神奈川電気の社長をやっておられた松田福一郎さん。この方は美術書。随分良い物がたくさんありま […]
-
あの作家は●月生まれだった
2017/08/30
あの作家は●月生まれだった<9月編>
今月ご紹介する作家は、棟方志功・正岡子規・谷崎松子の3名です。 棟方志功(むなかた しこう) 明治36年9月5日(一九〇三)生 昭和50年9月13日(一九七五)没 版画家。青森県生。長嶋尋常小学校卒。独学で洋画を学び、帝展入選。古川龍生・川上澄生の影響で木版画を志す。原始美術にも似た力強い「板画」を […]
-
古書通信
2017/08/28
二宮金次郎伝―「報徳記」「二宮翁夜話」ほか(上)【日本古書通信 編集長だより20】
二宮金次郎が最初に農村復興の仕法を実施した桜町(現・栃木県真岡市)が私の在所の隣町ということもあり、いつか詳しい伝記を読みたいと考えていたが、機会がなく何十年もたってしまった。 最近、日本の財政赤字が一千兆円を超し、歴代内閣も財政再建を第一目標に掲げるのに、赤字は増える一方で改善の目途はどうみても […]
コラム
本コラム欄では、八木書店の出版物に関わる紹介文や、『日本古書通信』編集長の日記、会社の歴史などを掲載いたします。ぜひご覧ください。