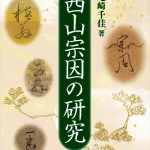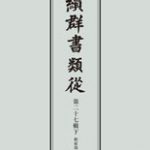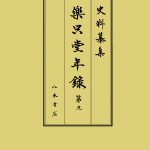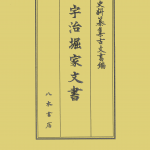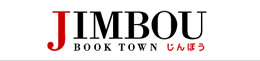-
やさしい茶の歴史
2024/06/18
鎌倉時代中期の喫茶文化 その三――やさしい茶の歴史(十四)(橋本素子)
鎌倉時代の禅宗寺院における茶の研究 今回は、鎌倉中期の禅宗寺院と茶との関わりを見ていく。 現存する鎌倉前期に建立された禅宗寺院には建仁寺・寿福寺、中期には東福寺などがある。いずれも禅と共に顕密などが勉強できる兼修寺院であった。鎌倉中期になりようやく、曹洞宗の永平寺、臨済宗の建長寺といった、本格的な禅 […]
-
コラム
2024/04/4
〈言葉〉と〈行為〉のあいだ ―西山宗因の〈心〉を探る―(尾崎千佳)
西山宗因の生涯と研究史 西山宗因は、慶長10年(1605)、加藤清正家臣の子として肥後熊本に生まれた。青年時代は加藤家家老に仕えていたが、同家改易により牢人し、29歳の寛永10年(1633)、上京して連歌師に転身する。正保4年(1647)、43歳にして摂津中島天満宮の連歌所宗匠に就任したのち、大名・ […]
-
出版部
2023/09/19
イエズス会が刊行した文法書を読む―『天草版ラテン文典巻一全釈』刊行の弁―
「天草版ラテン文典」とは 「天草版ラテン文典」(1594年天草刊)は、イエズス会が刊行したキリシタン版日本語文典3種の最初の文典であり、ラテン文法の枠組みで日本語を論じた初の文法書である。 という教科書的な一行なら、今やchatGPTでも書けそうだが、「天草版ラテン文典」の原文に即して、その日本語文 […]
-
やさしい茶の歴史
2023/07/4
鎌倉時代中期の煎茶法と点茶法の茶――やさしい茶の歴史(十三)(橋本素子)
醍醐寺で回し飲みされた茶 鎌倉中期には、平安前期時代以来の唐風喫茶文化、茶を煮だして飲む「煎茶法」の茶と、平安時代末期以来の宋風喫茶文化、抹茶に湯を注いで飲む「点茶法」の茶が併存していた。 寺院の法会や修法などでは、平安時代から引き続いて、煎茶法の茶を使用することが見られた。 たとえば、建長8年(1 […]
-
やさしい茶の歴史
2023/06/5
鎌倉時代中期の喫茶文化 その二——やさしい茶の歴史(十二)(橋本素子)
西大寺大茶盛について 今回は、鎌倉時代中期に活躍した僧侶で、茶との関りが深いとされる、叡尊と忍性を取り上げる。 叡尊といえば、西大寺で行われる茶を使用する2つの年中行事を創始した人物として知られている。 ひとつは西大寺大茶盛である。寺伝によると、暦仁2年(1239)正月、年始修法、すなわち修正会(し […]
-
やさしい茶の歴史
2023/05/29
鎌倉時代中期の喫茶文化 その一——やさしい茶の歴史(十一)(橋本素子)
今回は、鎌倉時代中期、貞応元年~弘安10年(1222~1287)の喫茶文化の様子を見ていこう。鎌倉中期は、承久の乱後、前半は比較的政治的に安定していたものの、後半には元寇があり、次第に政権も社会も不安定になる時代である。 相変わらず喫茶文化の様子を示す史料の点数自体は少ないものの、その内容は豊かであ […]
-
柳澤吉保を知る
2023/01/10
柳澤吉保を知る 第14回: 六義園(二)―桂昌院の楽しんだプレ六義園―(宮川葉子)
はじめに 前田綱紀の上地(あげち、幕府没収地)拝領から丸8年。 元禄15年(1702)7月5日、吉保設計の駒込の別墅(べっしょ)の庭園は完成した。 和歌の浦を写し取り、筑山や泉水をふんだんに配置、野趣あふれるそれであった。 これを正式に六義園と呼ぶのは3箇月半後の10月21日。 この日、当地に赴いた […]
-
やさしい茶の歴史
2022/12/1
明恵と茶 その二——やさしい茶の歴史(十)(橋本素子)
明恵の「駒の蹄影」伝説 前回の明恵の「深瀬三本木」伝説に引き続き、「駒の蹄影」(こまのあしかげ)伝説にも触れておこう。 まず「駒の蹄影」伝説の内容である。 ある日、宇治を訪れた明恵は、宇治の人々が茶実の蒔き方が分からず困っていたところに差し掛かった。そこで「栂山の尾の上の茶の木分け植ゑて あとぞ生ふ […]
-
出版部
2022/10/6
安保氏の故郷を訪ねて その4〔最終回〕(編集者・M)
金鑚神社(多宝塔) 金鑚神社は、埼玉県児玉郡神川町字二ノ宮にある神社。式内社、武蔵国五宮(一説には、地名にあるように二宮とされる)。旧社格は官幣中社で、現在は神社本庁の別表神社である。御獄山(標高343.4m)山麓に鎮座し、社殿の背後にある御室山(御室ヶ獄)を御神体として祀る。山を神体山とするため、 […]
-
出版部
2022/10/4
安保氏の故郷を訪ねて その3(編集者・M)
大瀧山幸春院道雲寺 幸春院は元阿保の西、JR八高線に近い神川町関口にある曹洞宗の寺院である。本寺は、安保直(忠)実の開基と伝えられている。直実は、建武3年(1336)没、法名幸春院真応実道。 〔図1 幸春院 本堂〕 直実は、京都に住み、足利尊氏の侍所執事である高師直とともに行動していた。貞和4年(1 […]