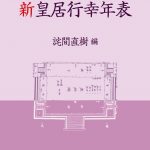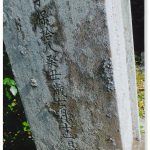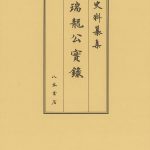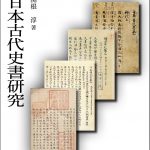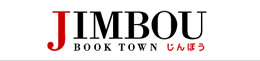-
出版部
2022/09/2
安保氏の故郷を訪ねて その1(編集者・M)
今年の大河ドラマは「鎌倉殿の13人」である。各地で関連の展示や催し物が開かれて盛り上がり、物語も佳境に入ってきた。今春、10年越しでようやく史料纂集古文書編『安保文書』を刊行することが出来た。鎌倉時代の初めに、歴史に登場してくるのが安保氏の祖、実光である。『吾妻鏡』によれば、平家追討の際、源範頼の軍 […]
-
『新皇居行幸年表』編集余滴
2022/08/31
平城宮の内裏と西宮 ―『新皇居行幸年表』編集余滴4(詫間直樹)
奈良時代の皇居に関わる表記には、「内裏」のほかにも「中宮」(ちゅうぐう)、「中宮院」(ちゅうぐういん)、「西宮」(さいぐう)、「東宮」(とうぐう)などがあり、『新皇居行幸年表』の編集においては、これらの呼称を平城宮内のどこに比定すべきかという問題に直面した。このうち中宮・中宮院については平城宮の東区 […]
-
『新皇居行幸年表』編集余滴
2022/08/1
別殿行幸について ―『新皇居行幸年表』編集余滴3(詫間直樹)
別殿行幸とは 別殿行幸(べつでんぎょうこう)とは、天皇が方違えをする必要が生じた場合などにおいて、同じ皇居の区画の中で、清涼殿などの常御殿から別の殿舎に移御することをいう。通常は昼御座(ひのおまし)の御剣などを携えて夜中に吉方の殿舎に移り、一夜を明かして本殿に還御するものである。本来、行幸とは天皇が […]
-
やさしい茶の歴史
2022/08/1
明恵と茶——やさしい茶の歴史(九)(橋本素子)
明恵の茶に関わる一次史料 今回は、栄西と共に「茶祖」と言われ、「深瀬三本木」「駒の蹄影」といった複数の伝説に彩られている明恵(高弁)について見ていく。 まず今のところ、明恵において茶に関わる一次史料(同時代史料)は、二通の書状のみであることを確認しておきたい(以下意訳は筆者)。 鎌倉時代前期月未詳1 […]
-
やさしい茶の歴史
2022/07/27
栄西と茶——やさしい茶の歴史(八)(橋本素子)
栄西の入宋と茶 今回は、栄西と茶についてみていく。 実は、日本における「茶祖」と称される栄西ではあるが、茶に関わる史料は思うほど多くはない。『吾妻鏡』建保2年(1214)2月4日条の記事、あとは栄西自著の『興禅護国論』の一節と、『喫茶養生記』のみである。 ただし『興禅護国論』にみえる茶は、宋風喫茶文 […]
-
柳澤吉保を知る
2022/07/1
柳澤吉保を知る 第12回: 吉保の側室達―(三)4人の側室とその子女達(付)養女達―(宮川葉子)(その3)
(承前) 第2部:養女達 吉保の養女を「門葉譜」に随い年齢順に並べると、土佐子、永子、悦子、幾子となる。 (一)土佐子 土佐子は折井正利女。黒田丹治直重室。宝暦8年(1758)11月25日卒。享年79歳。 武蔵国高麗郡加治郷(現在の飯能)武陽山能仁時に葬られた。 彼女は、吉保亡き後の柳 […]
-
『新皇居行幸年表』編集余滴
2022/07/1
当梁年と内裏造営 ―『新皇居行幸年表』編集余滴2(詫間直樹)
平安時代中期以降、内裏あるいは里内裏が相次いで焼亡するが、朝廷はその都度、再建の努力を重ねてきた。『新皇居行幸年表』では当然こうした事柄の年月日を掲出しているが、年表という性格上、なぜそのような造営経過をたどったのかなどの具体的な理由までは記していない。そこで、今回は特に内裏の立柱・上棟の時期に影響 […]
-
出版部
2022/06/21
『瑞龍公実録』を読む(藤田英昭)
記録の少ない江戸時代初期の重要史料のひとつ、徳川林政史研究所所蔵の「瑞龍公実録(ずいりゅうこうじつろく)」が初めて全文翻刻された。本書は、尾張徳川家2代当主徳川光友(寛永2年〔1625〕~元禄13年〔1700〕)の事績録で、書名は法諡に由来する。このたびの出版には「瑞龍院様御代奉書并御書付類之写」も […]
-
柳澤吉保を知る
2022/06/21
柳澤吉保を知る 第12回: 吉保の側室達―(三)4人の側室とその子女達(付)養女達―(宮川葉子)(その2)
(承前) (七)柳子腹の保経 宝永7年6月22日、上月柳子は男児を生んだ(「福寿堂年録」。『新訂寛政重修諸家譜』〈第3、262頁〉は宝永3年誕生とする)。 七夜の6月27日、吉保は頼母(よりも)と命名した。 吉保は前年6月18日に六義園に隠遁しているから、頼母は六義園での誕生である。 正徳元年(17 […]
-
やさしい茶の歴史
2022/06/10
やさしい茶の歴史(七)(橋本素子)
宋風喫茶文化の伝来 前回までは、9世紀初めに伝来した唐風喫茶文化の受容とその広がりを見てきた。すなわち院政期までには、貴族社会と寺院社会に定着しており、これまで茶道史の通史で言われてきたように、廃れてはいなかった。 今回は、院政期から鎌倉時代初期にかけて、新たに伝来した喫茶文化である、宋風喫茶文化に […]
-
柳澤吉保を知る
2022/06/8
柳澤吉保を知る 第12回: 吉保の側室達―(三)4人の側室とその子女達(付)養女達―(宮川葉子)(その1)
はじめに コラム第5回~第7回で、吉保側室飯塚染子と正親町町子を見た。 第8回~第11回は、吉保の武田信玄への思いを133回忌執行に探り、吉保の寿影3本を中心に、甲斐源氏末裔としての吉保・吉里父子が故郷に飾った錦を追った。 今回は、第7回までで沙汰止みの吉保側室に戻り、染子・町子以外の4側室とその子 […]
-
『新皇居行幸年表』編集余滴
2022/06/3
江戸時代の朝覲行幸―『新皇居行幸年表』編集余滴1(詫間直樹)
この度刊行した『新皇居行幸年表』では、書名の通り皇居の変遷に加え行幸の事例についても確認できる限り採録しているが、全時代を通覧することで新たな課題が見つかることもある。ここでは、これまで十分に知られていない江戸時代の朝覲(ちようきん)行幸について述べることとしたい。朝覲行幸とは、天皇が太上天皇(上皇 […]
-
やさしい茶の歴史
2022/05/25
やさしい茶の歴史(六)(橋本素子)
北斗供の茶――茶は「仙薬」 今回は、院政期以降、密教の流行により盛んにおこなわれるようになった私的修法である、北斗供と御影供について見ていこう。 まず北斗供である。これは本尊として星曼荼羅(北斗曼荼羅)を掛け、息災や延命を祈る修法である。陰陽道や道教とも関係する。まず平安時代中期には、本命星(一生変 […]
-
出版部
2022/05/9
古代史書の通史を目指して―『日本古代史書研究』のよみどころ―(関根 淳)
六国史以前の史書と古事記偽書説 これまで、日本古代の史書に関する研究は六国史が主で、それ以前の史書にはなかなか光が当たらなかった。今回、上梓した『日本古代史書研究』はこれまで十分に検討されてこなかった六国史以前の史書の実像を探り、そのなかで『古事記』を1つの史書としてとらえ直している。そして、そこか […]
-
やさしい茶の歴史
2022/05/9
やさしい茶の歴史(五)(橋本素子)
仏教儀礼の種類と茶 今回は、入唐僧によって持ち帰られたものをもとに日本で行われた、平安時代の仏教儀礼などにおいて、茶を使う様子を見ていきたい。 仏教儀礼はその内容から、10世紀半ばまでの①護国思想の顕教儀礼、②護国思想の密教儀礼、摂関期以降加わる③私的な顕教儀礼、④私的な密教修法などが見られる(『王 […]
コラム
本コラム欄では、八木書店の出版物に関わる紹介文や、『日本古書通信』編集長の日記、会社の歴史などを掲載いたします。ぜひご覧ください。