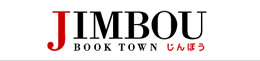鎌倉時代後期「金沢文庫文書」にみる喫茶文化(6)茶の生産について⑤―やさしい茶の歴史(二十一)(橋本素子)

下河辺庄赤岩郷の環境
今回は、まず下総国葛飾郡下河辺庄(しもこうべのしょう)赤岩郷の茶の生産について見ていく。下河辺庄赤岩郷は、現在の埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩・下赤岩にあたり、沖積低地ばかりではなく、下総台地の最西端の細長く北西に伸びる洪積台地の一部もあるが、総じて洪水の多い地域であった。
その赤岩郷では、南北朝期から茶の栽培が確認できる。そして少なくとも15年前には、松伏町上赤岩・下赤岩の古利根川沿いの自然堤防上に畦畔茶園が残る、昭和の茶生産に係る聞き取りが辛うじて可能な地域であった。
茶は、水害に比較的強い作物である。たとえば、京都府の城陽市などの木津川の河川敷では、抹茶の原料である碾茶(てんちゃ)を作るための覆下茶園(一定期間茶園全体に被覆し遮光して栽培する茶園)が広がる。これは、河川敷の平坦の水はけのよい砂地を利用し、独特の色良い碾茶を生産するためである。もちろん河川敷であるため、洪水のリスクは免れない。しかし洪水があっても、残留物等の掃除がなされれば、また翌年から生産が可能である。従来、種を蒔いて育てる実生栽培の茶樹の根は、直根であるため洪水にも耐え、倒れたり流れたりすることは少ないと説明されている。しかし現状を見ていると、実生栽培だけではなく苗を植えて育てた茶樹でも、倒れたり流れたりすることは少ないようである。むしろ、洪水は沃土を運ぶため、茶樹に良いとされる聞き取りも得ているくらいである。
いっぽう、中世の史料を見ても、例挙にいとまがないくらい洪水の多い地域に茶園がつくられた事例があり、茶樹が水害に強いことを物語っている。赤岩郷の事例はその一例となろう。
すなわち、洪水多発地帯である赤岩郷にとって、水害に強い茶は、比較的安定した収量・収入が期待される、環境に適応した作物であったといえよう。
赤岩郷の茶の生産
前置きが長くなったが、南北朝期の赤岩郷で茶が栽培されたことを示す史料を見よう。
(南北朝時代)「某書状」(『金沢文庫文書』二九九五号)
赤岩御茶、毎年十斤納め申し候や。当年も拾斤納め候処、この間の雑説に依り、路次等以ての外悪党蜂起候間、兎角了見致し候いて、引付候間、莫大な煩い無く候。結句御茶二斤、路次において憑みにせらるる者に所望せられ候いて出し候由申す間、様々に折檻し候。然ると雖も、無為持ち付け候間、上し候まま八斤
赤岩郷からは、名目は分からないが税として、毎年領主の称名寺へ茶10斤が納入されていた。この年も赤岩郷からは10斤が納められた。しかし、南北朝期の混乱により、赤岩郷から称名寺までに至る路次では、悪党が蜂起し治安が悪化しているのと噂で持ち切りであった。そのため、茶を運ぶ者は思案をめぐらし、然るべき人物に助力をお願いして、無事に通れるように手伝ってもらった。そのため、莫大な被害もなく運ぶことができた。ただし、そこはボランティアというわけにはいかず、茶を運んできた者は、助力をお願いした人物に茶2斤を所望されたので差し出した。これを称名寺に報告したところ、称名寺は茶を運んできた者を様々に折檻した。そうはいっても、無事に運んできたので、称名寺はひとまず8斤をそのまま受け取った、とでもなろうか。後の部分が欠けるため、ここまでの内容となる。
まず、製茶された茶10斤という量であるが、中世の度量衡は領主ごとに違うため、正確な数値を出すことが難しい。あくまで目安としてみると、1斤600グラムとして10斤で6,000グラム、生葉を製茶すると凡そ5分の1になることから、生葉にして30,000グラム=30キロ、当然それ以上の茶の生産があったものとみなすことができよう。
次に、茶が植えられていた場所である。同時代の荘園の事例をもとにすれば、荘園経営のための現地施設である荘政所もしくは荘内寺院の境内茶園が想定される。中世の赤岩郷は、「外河」=赤岩十四ケ村と、「内河」=赤岩三ケ村からなり、それぞれに政所が存在していた。これらに茶園が存在していた可能性もあろう。
なお、赤岩郷において茶が生産されていたことを示す史料はこの一点のみである。
伊賀国茶の入手
このほか、『金沢文庫文書』には「伊賀国茶」が見える。
元応元年(1319)九月五日付「金沢貞顕書状」(『金沢文庫文書』一九二号)
先日の参入、悦び存じ候。彼の時申さしめ候伊賀国茶〈一箱〉進らしめ候。又真乗院顕助法印許より、茶一両日の間到来し候。仍って一合別に進しめ候。又近日参らしめ候いて、池間の事沙汰いたすべく候。山は切候やらん。承るべき候。恐々謹言。
(元応元年)九月五日 貞顕(金沢)
方丈(釼阿)これを進せ候
この書状が書かれた元応元年9月5日に先立ち、金沢貞顕は称名寺方丈剱阿を邸宅に招いたが、その時「伊賀国茶」を送ってもらうことを告げていたようである。その伊賀茶が入手できたため、剱阿にも一箱を贈った。この箱の大きさはどのくらいのものであろうか、詳細は不明である。同時に貞顕の息子である京都仁和寺真乗院の顕助からも、ここ数日のうちに京都の茶が到来したので、それも一合をあわせて贈った。このとき貞顕が、どのような「つて」をもって伊賀茶を入手したのかも、詳細は不明である。
伊賀茶といえば、このすぐ後の南北朝時代に成立した『異制庭訓往来』「三月復状」の日本の茶の名産地を書き上げた個所にも、「伊賀八鳥(服部)」の地名が見える。丹生谷哲一氏は、ここに書き上げられ産地には拠点となる寺院があり、特に西大寺流(叡尊流)の寺院が多くみられること、伊賀服部にも叡尊によって再興された菩提寺があったことを指摘した。ただし、書き上げられている寺院は西大寺流に限られるものではなく、全体をみるとおおかたが顕密寺院であることは、かつて拙稿でも指摘した。また、ここに書き上げられた名産地は、『異制庭訓往来』が成立する前の時代、すなわち鎌倉時代後期に茶の生産が展開された、その成果であるともいえよう。
よってここからは、すでに鎌倉時代後期には、伊賀で茶の生産が広がっていたことが十分に想定できる。現にこの状況を背景にして、鎌倉にいる貞顕のもとへも伊賀茶がもたらされたのである。
以上のように、『金沢文庫文書』からは、鎌倉時代後期から南北朝期、北関東から近畿地方までの地域で、茶の生産が広がっていたことが確認されるのである。
参考文献
拙稿「下河辺庄における喫茶文化」(『金沢文庫研究』第324号、神奈川県立金沢文庫、2010年3月)。
同「鎌倉時代における宋式喫茶文化の受容と展開について―顕密寺院を中心に―」(『寧楽史苑』第46号、奈良女子大学史学会、2001年)。
*今回の史料はいずれも神奈川県立金沢文庫「金沢文庫文書データベース」による。(2025年6月16日最終閲覧)
https://kanazawabunko-db.pen-kanagawa.ed.jp/
【今回の八木書店の本】
『異制庭訓往来』(『群書類従 第九輯 消息部〔オンデマンド版〕』、続群書類従完成会発行、八木書店、2013年、474頁)

・八木書店コラム「やさしい茶の歴史」(橋本素子) バックナンバー

橋本素子(はしもともとこ)
1965年岩手県生まれ。神奈川県出身
奈良女子大学大学院文学研究科修了
元(公社)京都府茶業会議所学識経験理事
現在、京都芸術大学非常勤講師
〔主要著書・論文〕
『中世の喫茶文化―儀礼の茶から「茶の湯」へ―』(吉川弘文館、2018年)
『日本茶の歴史』(淡交社、2016年)
『講座日本茶の湯全史 第一巻中世』(茶の湯文化学会編、思文閣出版、共著、2013年)
「宇治茶の伝説と史実」(第18回櫻井徳太郎賞受賞論文・作文集『歴史民俗研究』、板橋区教育委員会、2020年)
「中世後期「御成」における喫茶文化の受容について」(『茶の湯文化学』26、2016年)