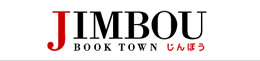鎌倉時代後期 「金沢文庫文書」にみる喫茶文化(5)茶の生産について④―やさしい茶の歴史(二〇)(橋本素子)

下総国土橋東禅寺の茶
前回の武蔵国金沢称名寺に続いて、今回は房総地域(安房・上総・下総=現千葉県)の茶について見ていきたい。
房総地域で茶の生産が行われていることには、あまりなじみがないかもしれないが、現在でも成田市などで茶が生産されている。それに今回取り上げる東禅寺のある旧下総国千田(ちだ)庄の荘域や上総国永興寺門前などには、それがいつ植えられたものか分からない茶の木や、昭和時代の製茶の記憶があるように、温暖な気候を背景に茶の生産が行われてきた歴史がある。
まず、称名寺末寺の下総国土橋(現千葉県香取郡多古町)の東禅寺境内茶園で茶が作られていた史料から見ていこう。
年未詳正月二十二日付「湛睿書状」(『金沢文庫文書』一八二〇号)
僧を以って申し入る旨候。委細尋ね聞こし食され候わば、悦び存じ候。また下品に候と雖も、仙茶一裹、推進せしめ候。乏少の至り、その憚り少なからず候。恐々謹言。
正月廿二日 湛睿
謹上 中村弥六殿
差出の湛睿は、暦応2年(1339)に称名寺第三代長老(住持)となるが、それに先立つ嘉暦元年(1326)には東禅寺住持となり、称名寺との間を頻繁に往復していた。充所の中村氏は、地元千田庄中村郷を本拠とする千葉氏被官であり守護代も務めた。よってこの書状は、湛睿が東禅寺住持をつとめていた時期のものである。おそらく前欠部分には正月ということもあり新年の御礼(挨拶)、あるいは依頼された祈祷の報告などが書かれていたものとみられる。そしてここには、湛睿から中村弥六へ「仙茶」を一包み送ったことが記されている。中世の寺院において、新年の御礼の際や祈祷の報告書「巻数」とともに茶を送ることにはよく見られることである。
なお湛睿は、東禅寺茶について「下品」と言っている。これは「粗品ですが」とでも意訳されるもので、あくまで謙った言い方であり、実際に「下品」かどうかは別問題である。また「仙茶」については、音が同じことから「煎茶」(煮出し茶)とする説があるが、実はその典拠がない。『金沢文庫文書』二九一二号には、「世に世にめでたき仙茶、進らせ候らんと」とみえるように、珍重されるものであった。おそらく、抹茶であろうが煮出し茶であろうがどちらでも可能性があり、新年の祈祷などの際に仏前に供えられたことにより、神仏の加護が期待される茶のこととみられる。さらに「乏少の至り、その憚り少なからず」は、「少しばかりで、恐縮ですが」とでもなろう。
四月七日付「湛睿書状」(『金沢文庫文書』一八二八号)
畏み言上せしめ候。抑も、土橋より末茶□箱進上せしめ候。この趣を以って、申し入れせしめ給い候。恐惶謹言。
卯月七日 湛睿〈上〉(花押)
道如御房
この書状も前半部分を欠く。後半部分には東禅寺にいる湛睿から称名寺へ、末茶(抹茶)を贈ったことが記されている。
年月日未詳「湛睿書状」(『金沢文庫文書』一九〇二号)
逐って啓す
当年の所出物においては、持円房を以って申し入る旨候。御意を懸けられ候わば、恐悦に候。この条真実本望に候。又、連々申し入るべく候なり。兼ねて又、下品に候と雖も、当寺常住茶進らしめ候。本より下品の上、路地の作法、察し申さしめ候。
こんどは、書状の追而書(追伸)部分のみが残ったものである。東禅寺の湛睿が称名寺に対して「東禅寺常住茶」を贈ったことがわかる。ここでも「下品」とあるが、一八二〇号と同様に、謙った言い方である。「路地の作法」とは、鎌倉時代末期から南北朝期にあって、土橋から称名寺までの道中の治安が乱れている様子を指しているものと見られる。
このように、東禅寺では境内で茶園を作り、それを地元の有力者や称名寺などに贈与していたことが抽出されるのである。
房総地域からの茶
このほか、具体的な寺院名は不明であるが、房総地域の寺院から鎌倉の極楽寺へ、茶が送られている事例を見る。
年未詳十一月三日付「如信書状」(『金沢文庫文書』二〇一四)
去る頃御音信に預かり候の条、喜悦に候。抑も、熊野御参詣の由、承り候条、浦山敷く思し奉り候。堯林御房同道仕るべく候の由、申され候。日限を承るべく候とて、状を進らせ候。又ひろ三くらより状を進せられ候。ひほの候も添えて候。又引茶一裹進らしめ候。乏少の至恐れ存じ候。介殿鎌倉に上り候。茶共引き立て候いて、恵俊御房・空本御房、茶をも進らせず候条心もとなく候。喜悦に候。事々後信を期し候。恐々謹言。
十一月三日 如信(花押)
謹上 勧学院〈御侍者〉
福島金治氏によると、この書状は、房総地域に住んでした如信から、極楽寺勧学院へ充てたものであるという。如信は千葉氏一族と親しく、「三くら」は東禅寺がある千田庄にある地名で、極楽寺の末寺があったとみられる場所であり、一九九九号には「三倉寺」が見えるという。その三倉から如信を経由して勧学院へは、書状とともに「ひぼ」(紐)が進上されている。これとともに、如信から勧学院へは、この書状と茶一包みが送られたのである。書状の中で如信は、介殿=千葉介貞胤が鎌倉に上っているにも関わらず、恵俊や空本が茶を出すことができなかったことが気がかりであったとしている。このように鎌倉時代後期にあっても、茶の流通量はまだまだ十分とはいえず、時に客人に対して出すことができなかったように、ないところにはないということが分かる史料でもある。
上総国三ヶ谷永興寺の茶
さらに東禅寺の末寺である上総国三ヶ谷永興寺(さんがやえいこうじ)でも、茶を生産していた。
年未詳六月一七日付「土橋知事書状」(『金沢文庫文書』二五七一号)
京都近国静かならず候の由、千葉より承り候。如何聞こし召され候。心もとなく候。又奥州難儀の由伝え承り候。鎌倉中は何の体に候覧と、心もとなく候。兼ねて又、御茶〈一袋〉幷に乾飯〈三斗〉進らしめ候。三ケ谷より御茶同じく進らせ候。又長老より上代の事仰せを蒙り候。麦時煩い候の間、行者を遣わし静謐に仕り候。此等の子細箕田入道定めて申され候か。秋に成りて候いて、何様にも煩い候いぬと存ぜしめ候。その内御量りあるべく候。諸事後信を期し候。恐惶謹言。
六月十七日 土橋知事(花押)
進上 東禅寺〈御侍者〉
土橋東禅寺知事から称名寺にいる湛睿へは、東禅寺茶とともに、三ケ谷永興寺茶が送られた。東禅寺では、境内茶園の茶だけではなく末寺永興寺から進上された茶も保有し、それらを本寺称名寺へ送っていたのである。このように寺院は、自園での生産、税や贈与で集まった茶を、さらに他者へ贈与するなど、小規模ながらも茶の集散地ともなっていたのである。
以上、鎌倉時代後期から南北朝期の房総地域では、下総国土橋、房総地域の某所、上総国三ケ谷と複数の真言律宗の寺院境内で茶の生産が行われていたことが抽出された。ただしこれらの事例をもって、鎌倉後期から南北朝期の房総地域において喫茶文化が真言律宗の特質であると結論付けることは早計であろう。なぜならば、南北朝期の房総地域の日蓮宗寺院でも、闘茶をはじめとする喫茶文化の受容を示す史料が確認できるからである。
*
『テーマ展 鎌倉時代の茶』(福島金治氏担当)神奈川県立金沢文庫 1998年、38頁。
今回の文書はすべて『金沢文庫古文書』金沢文庫 1952年―61年。
・八木書店コラム「やさしい茶の歴史」(橋本素子) バックナンバー

橋本素子(はしもともとこ)
1965年岩手県生まれ。神奈川県出身
奈良女子大学大学院文学研究科修了
元(公社)京都府茶業会議所学識経験理事
現在、京都芸術大学非常勤講師
〔主要著書・論文〕
『中世の喫茶文化―儀礼の茶から「茶の湯」へ―』(吉川弘文館、2018年)
『日本茶の歴史』(淡交社、2016年)
『講座日本茶の湯全史 第一巻中世』(茶の湯文化学会編、思文閣出版、共著、2013年)
「宇治茶の伝説と史実」(第18回櫻井徳太郎賞受賞論文・作文集『歴史民俗研究』、板橋区教育委員会、2020年)
「中世後期「御成」における喫茶文化の受容について」(『茶の湯文化学』26、2016年)