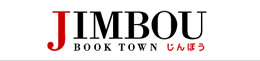鎌倉時代後期 「金沢文庫文書」にみる喫茶文化(4)茶の生産について③―やさしい茶の歴史(十九)(橋本素子)

称名寺茶成立の経緯
今回は、金沢称名寺(現横浜市金沢区)の境内に作られた茶園と、そこから生産された茶について見ていこう。
鎌倉時代中期までは、東国で茶の消費が行われていたことは確認できるが、生産が行われたことは確認されていない。ようやく鎌倉時代後期になって、茶が生産されていたことが確認できるようになる。そのひとつが武蔵国金沢称名寺である。
真言律宗(西大寺派)称名寺は鎌倉極楽寺の末寺であり、極楽寺は奈良西大寺の末寺である。西大寺中興の祖叡尊と茶の関係や、西大寺境内茶園と忍性の関係については第十二回で述べた。また忍性は極楽寺を開いたが、忍性と茶にまつわる遺品として現在でも境内に千服茶臼が残る。これだけみれば、西大寺―極楽寺―称名寺と茶が伝播されたことが想定されがちである。しかしそれを示す史料はなく、また極楽寺で茶が栽培されたとされる史料も見えない。千服茶臼も構造的に茶臼かといえば疑問符が付く。そのため、称名寺で茶が栽培されるに至った経緯は、不明としかいえないのである。
茶園に垣を作る
それでは称名寺境内に茶園があったことが確認できる史料から見ていこう。
鎌倉時代1月28日付「覚恵書状」(『金沢文庫文書』991号)
改年の御慶賀、貴札の旨の如く、今においては事旧に候と雖も、猶以って幸甚に候い了んぬ。(中略)
一、 茶園かきの事、今日廿八、人やとい候いて、せさせ候。(中略)
諸事後信を期せしむべく候。恐惶謹言。
正月廿八日 覚恵(花押)
進上 東禅寺侍者御報
この書状は、称名寺僧の覚恵から下総国土橋東禅寺の湛睿へ充てたものである。すなわち、称名寺境内には茶園があり、それには「かき」=垣(垣根)を設けていた。現在の常識でいえば「茶垣」があるように、茶の木自体が垣になるものである。それにも関わらず、わざわざ人夫を雇ってまで垣がつくられたのはなぜか。
ここで注目されるのが、この書状が書かれた時期である。すなわち1月28日といえば、新芽が出る直前の時期である。同時代の鎌倉郊外で鹿や猪の存在が想定されるように、鎌倉に隣接し背後に山を持つ称名寺の境内茶園でも、獣害があったことは十分に想定されよう。ちなみに獣害の内容は、鹿は新芽を食べてしまうこと、猪は茶樹の根に近い部分にいるミミズなどを食べるため、まるでミニショベルカーのように土を掻き出してしまい、結果根がむき出しとなり茶の木が傷んでしまうことである。これらの獣害を防ぐため、新芽が出る前に垣を設けたのではなかろうか。なお現在でも、山間部にある栂尾高山寺の復元茶園では、周囲に垣を設けその上にネットを張ることによって、鹿の害を防いでいるのである。
新茶の季節
鎌倉時代後期の称名寺茶園では、例年旧暦2月末ごろから新茶が製茶されていた。
鎌倉時代後期2月29日付「金沢貞顕書状」(『金沢文庫文書』260号)
新茶定めて出来候歟。御随身あるべく候。
僧衆只今御座の間、下品左道の御時候、入御候いて、御覧ぜられ候わば、恐悦に候。明後日〈一日〉、早旦入御候わば、悦び入り候。毎事その時見参に入れ、申し承るべき所に候。恐惶謹言。
二月廿九日 貞顕
冒頭の文字を下げて書かれた個所は追而書(おってがき)=追伸で、今回はここに注目しよう。金沢貞顕は称名寺長老剱阿に対して「称名寺では新茶が出来ているころではないか。今度来るときには持ってきてください」と依頼している。旧暦2月29日前後では、かなり芽が小さい時期に摘採して製茶していたことになろう。この書状は、例年の状況から新茶を製茶したことを想定している段階であるが、次の史料は、製茶したことが確定する。
鎌倉時代後期2月30日付「金沢貞顕書状」(『金沢文庫文書』281号)
陸奥左馬助(大仏貞直)の許に候御妻こそ、息女の冷泉殿とて、御所に奉公候いつるが、一昨日他界候程に、御妻の非(悲)歎、申すばかりの事なく候の由、只今承り候。
一昨日の参拝、恐悦候いき。兼ねて又新茶一裹給い候い了んぬ。殊勝に候の間、自愛の外他なく候。恐惶謹言。
二月卅日 貞顕
前書状と同様に、冒頭の文字を下げて書いたところが追而書となる。本文は「一昨日」からはじまるが、貞顕が剱阿から新茶一包みを貰ったことを記す。これは称名寺茶であろうし、旧暦2月30日以前に製茶を行い貞顕の許に送られていたことになろう。
このように、称名寺では境内に茶園があり、旧暦2月末ころには新茶が作られていたことが抽出される。当時、抹茶であっても新茶は珍重されるものであった。さらには新茶の生産される時期にも幅がみられた。この新茶は、新茶の中でも初度茶と称し、最も珍重されるものであった。
剱阿自慢の称名寺茶
では称名寺茶は、どのような品質のものであったのであろうか。
鎌倉時代後期月日未詳「釼阿書状」(『金沢文庫文書』1158号)
先日磨り進せ候、下品に候の間、当寺茶一裹これを進せ候。是れ随分宜しく候の間、進上せしめ候。此の金堂の柱六・七本、未だ着岸仕らず候えども、土用以前に礎居(据)える計りと存じ候の間、昨日〈三日〉石を居え候。同じく柱二本を以って立て初め候。此の後連々柱到来仕り候わば、調え立つべく候。谷殿も心本なく思し食され候間、
貞顕は、たびたび称名寺に、葉茶を茶臼で磨って抹茶にしてもらうことを依頼していた。先日貞顕の依頼により称名寺で磨って返却した茶が、下品=品質が良くなかったので、改めて称名寺茶一包みを進上した。今回の称名寺茶は、ずいぶん品質のよいものであるため進上したのである、と見える。これによると、貞顕のもとには、称名寺茶以外の茶が届くことがあり、それも称名寺に抹茶に磨るように依頼していたことになろう。しかも今回そのような茶に対して、称名寺茶は品質の良いものであると剱阿が自負できるような出来であった。ただしこれはあくまでこの場合の比較の問題であり、それがすぐに名産地に書き上げられるような茶と評価されることとは別問題である。
まず大前提として、茶も農産物なので、同じ畑の茶であっても、年々味や品質は変わるものであり、ましてや製茶の上手下手によって、できる茶の品質にも差が出来る。
またこのすぐ後の南北朝期になると、当時の知っておくべき常識やあるべき姿を記した「往来物」には、全国の茶の名産地が書き上げられるようになる。たとえば『異制庭訓往来』には、東国の名産地として「武蔵国河越茶」が見えるが、称名寺茶は見えない。ほかの「往来物」にしても同様である。
よって茶の評判や良し悪しというものは、なんどきも相対的にみる必要があるのである。
*『金沢文庫文書』260・281・1158号は「金沢文庫文書データベース」による。
https://kanazawabunko-db.pen-kanagawa.ed.jp/
991号は『金沢文庫古文書 僧侶書状篇上』(神奈川県立金沢文庫、1952年)による。
【今回の八木書店の本】
『異制庭訓往来』(『群書類従 第九輯 消息部〔オンデマンド版〕』、続群書類従完成会発行、八木書店、2013年)

・八木書店コラム「やさしい茶の歴史」(橋本素子) バックナンバー

橋本素子(はしもともとこ)
1965年岩手県生まれ。神奈川県出身
奈良女子大学大学院文学研究科修了
元(公社)京都府茶業会議所学識経験理事
現在、京都芸術大学非常勤講師
〔主要著書・論文〕
『中世の喫茶文化―儀礼の茶から「茶の湯」へ―』(吉川弘文館、2018年)
『日本茶の歴史』(淡交社、2016年)
『講座日本茶の湯全史 第一巻中世』(茶の湯文化学会編、思文閣出版、共著、2013年)
「宇治茶の伝説と史実」(第18回櫻井徳太郎賞受賞論文・作文集『歴史民俗研究』、板橋区教育委員会、2020年)
「中世後期「御成」における喫茶文化の受容について」(『茶の湯文化学』26、2016年)