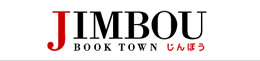鎌倉時代後期「金沢文庫文書」にみる喫茶文化(3)茶の生産について①—やさしい茶の歴史(十七)(橋本素子)

生産に係る史料の特徴
前回、前々回と、『金沢文庫文書』初出の茶道具である、茶筅と茶臼についてみた。今回はこれらを使用して飲む、茶の生産について見ていきたい。
ただし、『金沢文庫文書』は、生産でも茶の栽培について記載された史料が主であり、茶の加工についての記載がほとんどないことが特徴である。
なお鎌倉時代後期は、煎茶法(煮茶法)を特徴とする唐風喫茶文化と、点茶法を特徴とする宋風喫茶文化が併存していた。いずれも製法は、蒸すか湯がいて殺青(さっせい 酸化酵素の活性を、熱を加えて止める)し、揉まずに焙炉などで乾燥させ、茶瓶などに保存する。基本的に消費者が、煎茶法の場合にはそのままか粉末にし、点茶法の場合には粉末にして用いる。
種を播いて育てる
日本では、昭和30年代まで、種=茶実を播いて育てる実生栽培が主流であった。現在は、挿し木苗を植え育てる品種栽培が主流の宇治でも、昭和50年代まで実生茶園が存在していたとの聞き取りを得ている。当然のことながら、鎌倉時代は主に実生栽培が行われていた。
鎌倉時代後期二月七日付「縁西書状」(『金沢文庫文書』974号)には、
其の後何条御□□□(事候哉カ)、抑も思い懸けず□□。詫磨宿所後山に茶を殖え候。茶実少々拝領せしめ候わば、恐悦に候。毎事参拝の時を期し候。恐々謹言。
二月七日 縁西(花押)
金沢長老〈御侍者〉
とある。ここにみえる「詫磨」とは、鎌倉の宅間ヶ谷のことである。そこに住まう縁西は、「宿所の裏山に茶を殖えたい。そのために茶実をいただきたい」と、称名寺の長老剱阿に依頼している。つまり茶は、実生栽培で増やすものであった。
年未詳「某書状」(『金沢文庫文書』3403号)にも、
申し候心地して[ ]候えども、茶の実少し欲しく候こそ給わりて候しを、悪く植え候いて、生(お)いも出で候わぬほどに、さのみ難しく候えども、給わり候わば、返す返す悦び覚えさせ、
との一文がある。「茶実を少し欲しいと思いいただいたのだが、悪く植えてしまったようで、発芽しなかった。このように実生栽培は難しいものではあるが、改めて茶の実をいただけば、とてもうれしく思います」、となろうか。一度だけではうまく発芽せず、リトライを余儀なくされるほど、実生栽培は発芽率が低いものである。江戸時代の農書『農業全書』などを見ても、茶実を一か所にぐるりと円に2、30粒播いてもすべて発芽して育つことはなく、数本でも発芽し育てばよい方であった。
茶樹は、播種し発芽してから、早くて3、4年目に、最初の摘採ができる。
茶摘み(摘採)
次に、茶摘み=茶葉摘採についてである。
まずその回数についてであるが、『金沢文庫文書』のなかで最多回数は、5番である。年月日未詳「湛睿書状」(『金沢文庫文書』1892号)の1条には、
一、今年茶五番まで取りて候。尋ね申し候は終るべきの由、内々物語り申し候了んぬ。全分未だ道行かず候。
とある。
「番」とは、摘採回数のことである。このうち「1番茶」が「新茶」となるが、摘採は1度で終わるものではない。実生の場合には茶の木1株ごとに茶葉の育成速度が違ってくるため、それごとに時期を見極め摘採する必要がある。よってひとつの「番」の期間には、複数日が設定されていた。鎌倉時代後期月日未詳「某書状」(『金沢文庫文書』5111号)には、
貴寺第二度の新茶二褁給い候い了んぬ。当寺には希に候の間、御芳志謝し難く存じ候。
但し世間の人口に初度茶は代高直に候之
とある。これは、鎌倉極楽寺長老順忍から称名寺長老剱阿へ出された書状とみられるもので、意訳すると「称名寺の第二度の新茶を2袋いただきました。極楽寺にはめったにないものなので、御心遣いを大変ありがたく思っております。但し世間の噂では初度茶は代金が高値であるそうで」となろう。ここで、鎌倉時代末期、新茶の時期には「初度茶」・「第二度の新茶」と幅があり、新茶の1番目に摘採された茶=初度茶(いまでいう「走り」か)は、高値で取引されていたことがわかる。
なお、1番茶でも幅があるというのは、時代が下がるとその期間が明確になる。例えば戦国末期の永禄8年(1565)の上野国新田郡世良田長楽寺では4月10日から5月5日まで、江戸時代の宇治でも約1か月に及ぶとされていた。(『京都御役所向大概覚書』)
次に5番までの時期を考えると、概ね旧暦3月から6月の間に3番まで済ませ、夏を越して秋に残りの2番を摘採するくらいが適当である。南北朝期になるが、康永3年(1344)6月に比定される「某書状」(『金沢文庫文書』4735号)には、「はや三番まで取りて候」とあることが、これを裏付ける。
なお、この史料では5番まで摘採したが、それでも「全分未だ道行かず」、つまりすべて摘採しきれなかったとある。今と違って茶葉の芽数(めかず)までは管理されず、その年々の気候もあいまって、年によって収穫量の増減があった。このように摘採しきれない場合には、そのまま放置されたようである。そのあとの茶園管理が気になる所である。
【今回の八木書店の本】
史料纂集古記録編 第135回配本 長楽寺永禄日記(続群書類従完成会発行、2003年)

・八木書店コラム「やさしい茶の歴史」(橋本素子) バックナンバー

橋本素子(はしもともとこ)
1965年岩手県生まれ。神奈川県出身
奈良女子大学大学院文学研究科修了
元(公社)京都府茶業会議所学識経験理事
現在、京都芸術大学非常勤講師
〔主要著書・論文〕
『中世の喫茶文化―儀礼の茶から「茶の湯」へ―』(吉川弘文館、2018年)
『日本茶の歴史』(淡交社、2016年)
『講座日本茶の湯全史 第一巻中世』(茶の湯文化学会編、思文閣出版、共著、2013年)
「宇治茶の伝説と史実」(第18回櫻井徳太郎賞受賞論文・作文集『歴史民俗研究』、板橋区教育委員会、2020年)
「中世後期「御成」における喫茶文化の受容について」(『茶の湯文化学』26、2016年)