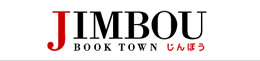-
やさしい茶の歴史
2022/04/6
やさしい茶の歴史(四)(橋本素子)
入唐僧と喫茶文化 第1回に述べた平安時代前期の永忠・最澄・空海等のあとも、唐風喫茶文化は、何度もさまざまな人々によって持ち帰られたものと見られる。 そこで今回は、視点を国外に向け、中国の唐に留学した僧侶「入唐僧」が、唐風喫茶文化をどのような場面で体験したのか、平安時代前期の円仁と中期の円珍の事例を見 […]
-
やさしい茶の歴史
2022/03/10
やさしい茶の歴史(三)(橋本素子)
『江家次第』に見る「季御読経」の茶 今回は、平安時代、宮中における仏教行事である「季御読経(きのみどきょう)」において、引き茶として振る舞われた茶が、どのようにして飲まれていたのかを見ていく。 なお、儀礼は毎回判で押したように同じことを繰り返すとは限らない。むしろ、その時その時の事情で変わるものと捉 […]
-
やさしい茶の歴史
2022/02/16
やさしい茶の歴史(二)(橋本素子)
日本最古の茶園・大内裏茶園 前回、弘仁6年(815)6月3日、嵯峨天皇は、畿内等で茶を植え、それを毎年献上するように命じたが、実際にそれが行われたかどうかわからないと書いた。また、永忠・最澄・空海ら入唐僧が、帰国後茶をどのように調達していたのかわからないとも書いた。 そのような中で唯一、嵯峨天皇の命 […]
-
やさしい茶の歴史
2022/02/3
やさしい茶の歴史(一)(橋本素子)
喫茶文化史とは何か これまで、茶の歴史を扱う分野は、「茶道史」や農業史のなかの「茶業史」であった。特に茶道史では、千利休が「茶の湯」を大成するまでのひとすじの流れを描くものであった。しかし、その流れから外れる事柄は、「茶の湯」の通史に無理に引き付けて理解されたり、逆に全く評価されなかったりと、フラッ […]