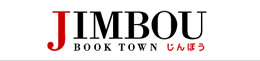柳澤吉保を知る 第13回: 六義園(一)―初期六義園の誕生まで―(宮川葉子)
(三)作庭の実際
六義園作庭の経緯は、『年録』には見えない。
理由は、元禄15年(1702)4月6日の、神田橋の柳澤家上屋敷火災(第3・216頁)での記録類焼失にあろう。
それを補うのが、『松陰日記』(まつかげにっき)である。
当該は、吉保側室正親町町子の手になる作品(以下『松陰日記』の引用は、宮川葉子『柳沢家の古典学(上)―『松陰日記』―』〈平成19年・新典社〉による)。
その「十四、玉かしは」に次がある。
駒込の山里はいと広らかなる所を占めて、山水の便りおかしき辺りなるを、年月さるべき家居造り占め、庭なども二なく面白き様に催し給。
御自らは御暇なくておはせず。
家人日々に行き通ひて、さる方の造り出べき様、絵に描きて奉りつるを、明け暮れ御覧じ入れて、とかく掟てさせ給ふ程に、さ言へど覚束なからず。
世の中にはかゝる事、例の耳敏く聞ゝて、何くれの石、植木やうのもの、いさゝかも心ある形したるは皆此御料にとて奉りつ(525~526頁)。
以下3点に分け考察したい。
(四)「十四、玉かしは」①
「山水の便りおかしき辺り」とは、「山と水の配合が実に風流な一帯」の意味であろう。
作庭途上の六義園かに見えるが、「庭なども二なく面白き様に催し給」と続き、「面白き様に催し」た庭こそが吉保設計の六義園のことらしい。
すると「山水の便りおかしき辺り」は、吉保拝領当時の前田家下屋敷の庭を語るものと見た方が穏当であろう。
一方、尊経閣文庫(そんけいかくぶんこ。和漢の典籍・文書類・綱紀の収集品を蔵する前田家の図書館)だけ見ても、綱紀の学芸への造詣深さは十分に知れる。
しかもその先祖利長(利長―利常―光高―綱紀)時代から、加賀藩主の庭園であった金沢市小立野(こだちの)の兼六園を勘案すると、吉保拝領以前から、かの地には「山水の便りおかしき」庭園があったのではないかと思い至る。
吉保はそれを改作。新たな思想を込め造り上げた、それが六義園なのではなかろうか。
(五)「十四、玉かしは」②
「御自らは御暇なくておはせず。家人日々に行き通ひて、さる方の造り出べき様、絵に描きて奉りつる」に移ろう。
公務多忙で自身で足が運べない吉保は作庭の指示を出す。
請けた家臣は進捗状況を絵に描き逐条報告した。
その方法で工事は進んで行ったのである。
吉保の要望に呼吸を合わせられる有能な人材を確保していたのは吉保の手腕。
因みに当時吉保は川越城主。
定府(じょうふ。参勤交代せず江戸に常住)であったから、領地経営もこの方法に依っていたし、甲斐国拝領以後も同様となる。